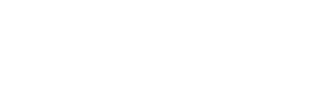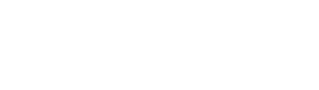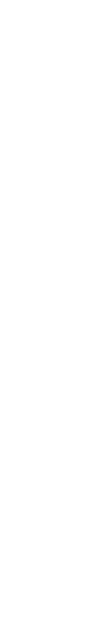NEWS
お知らせ
2025.03.30 |
歯の本数で寿命が変わる?健康寿命を延ばすために今できることとは? |
2025.03.30
歯の本数で寿命が変わる?健康寿命を延ばすために今できることとは?
こんにちは。加藤デンタルオフィス高崎です。
実は、“歯の本数”は私たちの健康寿命(健康で自立した生活ができる期間)に深く関係していることが、近年の研究で明らかになっています。噛む力が落ちると、栄養が偏るだけでなく、筋力や認知機能、心の健康にまで影響を与える可能性があるのです。
反対に、歯がしっかり残っている方は、よく噛んで食事を楽しめるだけでなく、活動的で若々しく過ごせる傾向にあります。だからこそ、歯の本数は「単なる見た目」ではなく、将来の自分の生活の質を守る“カギ”ともいえるのです。
今回は、歯の本数と健康寿命の関係、歯を守るための予防法、万が一歯を失ったときの対策までを解説していきます。いつまでも元気で過ごすために、今できることから一緒に始めてみませんか?
1.こんなお悩みありませんか?

- 「年齢とともに歯の本数が減ると健康に影響するって本当?」
- 「歯が少なくなると、食事が楽しめなくなるの?」
- 「健康寿命を延ばすために、歯を守る方法が知りたい!」
最近では「健康寿命」という言葉をよく耳にするようになりましたね。これは、「介護を受けず、自立して元気に暮らせる期間」のことを指します。
そして実は、この健康寿命を左右する大きなカギの一つが「歯の本数」なんです。
「今はまだ問題ないけど、将来が心配」
「歯が減ってきて、食事がしにくくなってきた」
そんなお悩みがある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
2.健康寿命とは?歯と全身の健康の関係
 「歯の健康が、体全体の健康にも関係している」
「歯の健康が、体全体の健康にも関係している」
最近よく耳にするようになった言葉ですが、実は本当にその通りなんです。
健康寿命と平均寿命、どう違うの?
| ★平均寿命 | 生まれてから亡くなるまでの期間(人生の長さ) |
| ★健康寿命 | 介護を受けず、自立して元気に生活できる期間 |
たとえば日本では…
- 平均寿命:男性 約81.6歳、女性 約87.7歳
- 健康寿命:男性 約72.7歳、女性 約75.4歳
この差、なんと約10年もあるんです。
つまり、「長生きできても、最後の10年ほどは介護が必要になるケースが多い」という現実があります。
なぜ「歯の本数」が健康寿命に関係するの?
歯が少なくなると、「しっかり噛む力」が弱くなり、次のような影響が出てきます。
✅噛めないことで起きる健康への影響
- 食べ物の選択肢が減る
→ やわらかい物中心になり、栄養が偏りがちに - 栄養不足・筋力低下
→ 体力が落ち、転びやすくなったり疲れやすくなったり - 誤嚥(ごえん)のリスク増
→ 嚥下力が弱まり、誤って食べ物が気管に入ってしまうことも - 脳への刺激が減る
→ 認知症リスクの上昇と関係しているといわれています
「80歳で20本以上歯が残っている人」は、健康寿命が長いというデータもあり、歯の本数と健康の関係は無視できないものなんです。
歯の健康=全身の健康につながる理由
歯が元気でしっかり噛めると、こんな良いことがたくさんあります。
✔ 噛むことで脳が活性化
噛む刺激は脳に届き、記憶や判断力をキープするサポートになります。
✔ 顔や首の筋肉も鍛えられる
噛むことでお顔まわりの筋肉を使い、飲み込む力や表情の豊かさにもつながります。
✔ 歯周病は全身の病気と関係がある
・糖尿病
・心疾患
・誤嚥性肺炎
…など、歯周病を放っておくと、思わぬ病気を引き起こすリスクも。
だからこそ、お口の健康は“全身の健康”を守る土台なんです。
健康寿命を延ばすには?今からできる4つのこと
- 毎日の歯磨きをていねいに – 歯と歯ぐきの境目も意識してケア
- 定期的に歯科検診を受ける – 早期発見・早期治療で歯を守る
- 歯が抜けたら放置しない – 入れ歯・ブリッジ・インプラントなど、早めの対応が大切
- バランスの良い食生活を心がける – 噛みごたえのある食材も意識的に取り入れましょう
「もう歳だから仕方ない…」そう感じる必要はまったくありません。
正しいケアをすれば、年齢に関係なく、歯は守れます。
そして歯を守ることは、これからの人生を元気に、楽しく過ごすための土台です。
3.歯の本数と健康寿命の関係とは?
 歯の本数が多いか少ないかで、将来の健康リスクや生活の質がどう変わるのか——
歯の本数が多いか少ないかで、将来の健康リスクや生活の質がどう変わるのか——
最近は研究も進み、データとしてもいろいろなことがわかってきています。
歯が20本以上ある人と、少ない人の健康リスクの違い
人間の歯は、親知らずを除くと全部で28本。
そのうち「20本以上の歯がしっかり機能しているかどうか」が、ひとつの健康の指標として使われています。
なぜ“20本”が目安になるのか?
→ それは、20本以上の歯があると「ほとんどの食べ物を問題なく噛める」**と言われているからです。
✅20本以上の歯がある人の特徴
- 食事の選択肢が広がる(肉・野菜・繊維質など)
- 栄養バランスが整いやすく、体力や免疫力を維持しやすい
- 噛むことで脳や筋肉に刺激が届き、認知機能の低下を防ぎやすい
✅歯が少ない人に起こりやすいこと
- 柔らかい物ばかり選び、栄養の偏りが起きやすい
- 噛む刺激が少なくなり、脳の働きや反応が鈍くなる
- 嚥下機能が落ちて誤嚥のリスクが増える
- 姿勢やバランス感覚が乱れ、転倒リスクが高まる
つまり、歯の本数が少ないと、口の中だけでなく、全身にさまざまな影響が出やすくなるということなんです。
認知症や転倒リスクとの関係って?
歯の本数が少なくなることで、“噛む回数”や“咀嚼力”も低下します。
この「噛む」という動作は、単に食べるためだけでなく、脳を活性化するスイッチのような役割も担っているんですよ。
✔噛むことで脳が刺激される
- 記憶をつかさどる「海馬」などの部分が活性化
- 集中力や判断力を維持しやすくなる
- 噛む力が弱まると、認知機能の低下リスクが上がるという研究報告も
また、噛む力が落ちることで、食事の満足感が減り、意欲の低下につながることもあります。
✔噛めないことで転倒リスクが増える?
あまり知られていませんが、歯が少ない人ほど転倒するリスクが高いというデータもあります。
これは、噛むことで体幹の筋肉や姿勢を調整する機能が働いているためです。
「噛む=体のバランスを整える」
という、ちょっと意外なつながりがあるんですね。
最新の研究データが示す“歯の本数と健康寿命”
いくつかの研究をご紹介します。
✅20本以上の歯を保っている高齢者は、要介護状態になるリスクが低い
(厚生労働省「8020達成者調査」より)
✅歯が少ない人は、食事から摂れるたんぱく質やビタミンの量が少なく、サルコペニア(筋肉量の低下)になりやすい
(日本老年歯科医学会の報告)
✅認知症の方は、平均して残っている歯の本数が少ない傾向にある
(国立長寿医療研究センターの発表)
これらの研究結果からも、歯の本数を守ることは、健康寿命をのばすことに直結しているといえます。
「歯が少ないから、もう仕方ないかも…」
そう思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。
- 残っている歯をしっかり守る
- 抜けたところは放置せず、早めに噛める状態に戻す
- 歯科医院での定期的なケアを習慣にする
この3つを意識するだけで、これからの10年、20年が大きく変わってきます。
4.なぜ歯を失うと健康に影響するのか?
 歯が1本なくなるだけでも、「なんとなく噛みにくい」「反対側でばかり噛んでしまう」といった不便を感じることがありますよね。
歯が1本なくなるだけでも、「なんとなく噛みにくい」「反対側でばかり噛んでしまう」といった不便を感じることがありますよね。
でも実は、それだけでは終わらず、全身の健康や気持ちの面にもじわじわと影響が出てくるんです。
噛む力が低下すると、体にどんな影響が出るの?
「噛む」という動作は、単に食べるためだけじゃありません。
体のいろいろな部分とつながっていて、噛む力が弱まると、次のような問題が起こりやすくなります。
✅嚥下(えんげ)機能の低下
噛まずに飲み込みやすい食事が増えると、飲み込む力そのものも衰えてしまいます。
その結果、「誤嚥(ごえん)性肺炎」のリスクが高まります。
✅顔まわりの筋力が衰える
あご、舌、頬、首など、噛むときに使う筋肉が少しずつ弱ってしまい、
表情の乏しさや発音のしづらさにもつながります。
✅脳への刺激が減る
噛むたびに脳に伝わっていた刺激が減ってしまうと、認知機能の低下にも影響が出ると考えられています。
✅姿勢やバランスが崩れる
噛み合わせが悪くなると、体のバランスがくずれて肩こり・首の痛み・腰痛につながることもあります。
歯が少なくなると、栄養バランスが崩れやすい
歯を失うことで、食べられるものが限られてくることも多くなります。
たとえば、こんな食事の傾向に。
- 柔らかいもの(うどん・おかゆ・パンなど)ばかり選ぶようになる
- 肉や生野菜など「しっかり噛むもの」を避ける
- 噛み切りにくい繊維質(ごぼう・きのこ・こんにゃく)などを敬遠してしまう
すると、たんぱく質・ビタミン・ミネラル・食物繊維が不足しがちになり、
筋肉量の減少、便秘、免疫力低下などが起きやすくなります。
また、栄養不足はフレイル(虚弱状態)の原因のひとつでもあります。
✅つまり、歯が減る → 噛みにくくなる → 栄養が偏る → 体が弱るという負の連鎖が起きてしまうんです。
食事の楽しみが減ると、気持ちにも影響が…
「食べたいものが食べられない」
「口に入れる前に、食べやすいかどうかを気にしてしまう」
「人前で食べるのが恥ずかしい」
こういったことが重なると、食事が楽しい時間ではなくなってしまうこともあります。
するとどうなるかというと…
- 食事の回数や量が減ってしまう
- 外出や人と会う機会が減る
- 気分が沈みやすくなる、やる気がなくなる
こういった状態が続くと、心の健康にも大きく影響を与えてしまいます。
歯の問題は、「身体」だけでなく「心」にもつながっているんですね。
歯を1本失うだけでも、それをきっかけに体や心のバランスが崩れてしまうことがあります。
「たかが1本」ではなく、「1本でも多く守ること」が、これからの健康を守ることにつながるのです。
5.歯が少ないと食生活にどんな影響がある?
 「歯の本数が減ってきた」「うまく噛めなくなってきた」——そんなお悩みを抱えている患者様は、少なくありません。
「歯の本数が減ってきた」「うまく噛めなくなってきた」——そんなお悩みを抱えている患者様は、少なくありません。
よく噛めないと、避けがちな食品が増えてしまう
歯が少なくなると、噛む力が落ちてしまうため、硬いものや噛み応えのある食品を避ける傾向が出てきます。
たとえば、こんな食材が苦手になりやすいです:
- 生野菜(キャベツ、にんじんなどの繊維質が多いもの)
- 肉や魚(とくにかたまり肉や焼き魚)
- ごぼう、れんこん、こんにゃくなどの噛み切りにくい食材
- たくあん、するめ、フランスパンなど硬さのある食品
このような食品には、たんぱく質・ビタミン・ミネラル・食物繊維といった、身体の元気を保つために欠かせない栄養素がたっぷり含まれています。
避ける食品が増えると、自然と食事のバランスが偏り、次のようなリスクが出てきます。
⚠ 栄養不足のリスク
- 筋力が落ちやすくなる(サルコペニア)
- 免疫力が下がり、風邪や感染症にかかりやすくなる
- 便秘や肌荒れが起こりやすくなる
- 疲れやすい・集中力が続かない
しっかり噛めることは、ただの「食べやすさ」ではなく、体をつくる土台でもあるんです。
歯の本数と「食事の満足度」は深くつながっている
食事は単なる栄養補給だけでなく、「楽しみ」や「心の癒し」の時間でもありますよね。
でも、歯が少ないと…
- 「これ、噛めるかな?」と心配になる
- 食事のたびに気をつかう
- 家族や友人と同じものを食べられない
- 外食や旅行先で食事が楽しめなくなる
こうした体験が重なると、食事の時間そのものがストレスに変わってしまうこともあるんです。
実際に、歯が20本以上残っている高齢者の方は、食事に対する満足度が高く、「食べる楽しみがある」と感じている方の割合が多いという調査結果もあります。
✅つまり、「噛める=おいしく、楽しく食べられる」ということ。
この感覚があるだけで、毎日の生活にハリが出てきます。
噛めることが、健康寿命を延ばすカギに
「噛めないからやわらかいものでいいや」
「好きなものより食べやすいものを選んでいる」
そんな状態が続くと、体だけでなく、気持ちの元気も失われてしまいます。
しっかり噛めることには、こんなメリットがあります:
✅栄養をしっかり吸収できる
→ 消化を助けることで、食べた栄養がきちんと体に届きます。
✅脳が活性化する
→ 噛む刺激が脳に伝わり、記憶力や集中力の維持にもつながります。
✅飲み込む力(嚥下力)が鍛えられる
→ 誤嚥を防ぎ、誤嚥性肺炎などのリスクを減らします。
✅表情が豊かになり、会話もしやすくなる
→ 顔まわりの筋肉が活性化し、自然な笑顔が増える方も多いです。
噛めるというだけで、身体にも心にも、これだけの良い影響があるというのは、すごいことですよね。
「噛めない」「食べにくい」と感じるようになったときこそ、健康を見直すタイミングです。
6.8020運動とは?歯を守るための具体的な取り組み
 8020運動って何?それがなぜ大切なの?という基本的なところから、今日からできる歯を守るための習慣までご紹介していきます。
8020運動って何?それがなぜ大切なの?という基本的なところから、今日からできる歯を守るための習慣までご紹介していきます。
そもそも8020運動って何?
8020運動とは、「80歳になっても自分の歯を20本以上保ちましょう」という、厚生労働省と日本歯科医師会が進めている健康づくりの運動です。
なぜ「20本」なのかというと——
20本あれば、ほとんどの食べ物を不自由なく噛めると言われているからです。
しっかり噛める状態を保つことで…
- 食事を美味しく楽しめる
- 栄養がしっかり摂れる
- 脳や身体に良い刺激が伝わる
- 認知症や誤嚥、転倒などのリスクを抑えられる
✅つまり、歯を残すことは、健康寿命をのばすことにもつながるというわけですね。
80歳で20本の歯を残すために大切な3つのこと
1)毎日のオーラルケアの習慣づけ
自分の歯を長く使い続けるには、やっぱり毎日のケアが基本になります。
ただ磨けばいいというわけではなく、“正しく”ケアすることが大切です。
✅歯ブラシのポイント
- 毛先が広がってきたらすぐに交換(1ヶ月を目安に)
- 力を入れすぎず、優しく細かく動かす
- 歯と歯ぐきの境目や奥歯の裏もしっかり意識して磨く
✅歯間ケアも忘れずに
- 歯と歯のすき間に歯垢がたまりやすいので、フロスや歯間ブラシを併用しましょう
- 就寝前のケアは特に丁寧に!
✅口腔乾燥(ドライマウス)対策も重要
- 唾液は天然の抗菌剤。水分補給や軽いマッサージで唾液分泌を促すのもおすすめです。
2)定期的な歯科検診を受けること
「痛くなったら歯医者に行く」では、どうしても対処が遅れてしまいます。
歯周病やむし歯は、自覚症状が出る頃にはかなり進行していることが多いんです。
✅検診の目安:3〜6ヶ月に1回
- 歯石や着色の除去
- 歯ぐきの状態チェック
- 噛み合わせや詰め物のチェックなども行います
早期発見・早期対応ができれば、大切な歯を守れる確率がぐっと上がります。
3)歯を失ったままにしないこと
歯を1本失っただけでも、噛み合わせが乱れたり、他の歯に負担がかかったりして、連鎖的に他の歯もダメになってしまうことがあります。
✅歯を失ったら、放置せずに補うことが大切
- 入れ歯
- ブリッジ
- インプラント など、患者様に合った方法を選べます
「たった1本だから…」と油断せず、早めに噛める状態に戻しておくことが、他の歯を守るポイントです。
8020運動は、ただ歯の数を保つことを目指すだけの活動ではありません。
その目的は、人生の後半も好きな物を食べて、笑って、元気に過ごすための“土台づくり”にあります。
7.歯を失ったらどうする?早めの対策が健康寿命を延ばす
 「歯を1本抜いたけど、そのままにしてしまっている」「入れ歯にしようか迷っている」・・・
「歯を1本抜いたけど、そのままにしてしまっている」「入れ歯にしようか迷っている」・・・
歯を失ったままにしておくと、お口の中だけでなく、体全体の健康にもじわじわと影響が出てくることがあるんです。
歯を失ったら選べる3つの治療法
歯が抜けたあと、その部分をどう補うかには、いくつかの選択肢があります。
それぞれの特徴を、ざっくりと比較してみましょう。
① 入れ歯(義歯)
- 取り外しができて、複数の歯をまとめて補える
- 比較的費用が抑えられる
- 保険適用の範囲でも対応可能なケースが多い
- ただし、噛む力や安定感にはやや不安がある場合も
② ブリッジ
- 両隣の歯を削って橋渡しのようにして補う治療
- 見た目も自然で、固定式なので違和感が少ない
- ただし、健康な歯を削る必要があるため負担が大きいことも
③ インプラント
- あごの骨に人工の歯根を埋め込み、その上に被せ物をする治療
- 他の歯を削らずに済み、見た目も噛み心地も自然に近い
- 骨がしっかりしていれば、長く使える治療法
- 外科処置が必要で、費用や期間は他よりやや高め
どの治療にもメリット・デメリットがありますが、共通して言えるのは、**「早めに対処することで、周りの歯や骨への影響を最小限に抑えられる」**ということです。
放置すると…顎の骨がどんどん痩せてしまう?
「1本くらいなら大丈夫かな」と思ってそのままにしておくと、実は見えないところでどんどん変化が起こります。
✅放置することで起きやすい変化:
- あごの骨が痩せていく
歯が抜けた部分は、噛む刺激がなくなるため骨が吸収されて薄くなっていきます。
これは“骨が使われなくなる”ことで起こる自然な現象です。 - 周囲の歯が動いてくる
空いたスペースに向かって、隣の歯や噛み合う歯が傾いてきて、かみ合わせが乱れてきます。 - 噛むバランスが崩れる
片側ばかりで噛むようになったり、無意識に噛む力を逃がそうとして、他の歯に負担がかかります。
このように、1本の歯を失っただけでも、「周囲の歯」「噛む力」「骨の状態」すべてに悪影響が広がってしまうんです。
自分に合った治療法を選ぶには?
どの治療法が最適かは、患者様の年齢やお口の状態、ご希望によって変わってきます。
✅治療を選ぶときに考えておきたいポイント
- 他の歯に負担をかけたくないか?
→ インプラントが適している場合が多いです。 - 治療費をできるだけ抑えたいか?
→ 入れ歯や保険のブリッジを検討される方が多いです。 - 長期的に安定した噛み心地を求めているか?
→ インプラントや高精度なブリッジが候補になります。 - 外科処置に不安はあるか?
→ 手術が難しい方は入れ歯やブリッジの選択が現実的です。
どれが正解というものではなく、今の生活スタイルや将来の希望に合わせて選ぶことが大切です。
歯を失ってしまったとき、大切なのは「そのままにしないこと」。
放置せずにすぐに対応することで、周囲の歯や噛む力、骨の状態を守ることができるのです。
8.健康な歯を維持するための予防策
 「歯を失ってから治療する」よりも、「歯を失わないように予防する」ことのほうが、ずっと大切です。そして実は、そこまで難しいことをする必要はないんです。
「歯を失ってから治療する」よりも、「歯を失わないように予防する」ことのほうが、ずっと大切です。そして実は、そこまで難しいことをする必要はないんです。
正しい歯磨きとデンタルフロスの活用
歯磨きは、歯を守るためのいちばん基本的なケア。でも、「きちんと磨いているつもり」でも、実は汚れが落ちきっていないことって意外と多いんです。
✅正しい歯磨きのポイント
- 歯と歯ぐきの境目を意識して磨く
この境目に汚れがたまりやすく、歯周病の原因になりやすい部分です。 - 力を入れすぎない
ゴシゴシ磨くと歯ぐきが傷ついてしまうことも。優しく、小刻みに動かしましょう。 - 磨き残ししやすい場所は要チェック
奥歯の裏側、前歯の裏、歯と歯の間などは特に注意が必要です。
✅歯ブラシ+デンタルフロス・歯間ブラシ
- 歯と歯の間の汚れは、歯ブラシだけでは6割ほどしか落ちないといわれています。
フロスや歯間ブラシを取り入れることで、虫歯や歯周病のリスクを大きく下げられます。
1日1回でもいいので、寝る前のケアにフロスを使ってみてください。
はじめは少し面倒でも、慣れてくると「やらないと気持ち悪い」くらいになりますよ。
生活習慣を見直すことも歯の健康につながる
「生活習慣が歯に関係あるの?」と思われる方も多いのですが、実は大いに関係しています。
毎日の習慣の中で、歯や歯ぐきにダメージを与えてしまっていることもあるんです。
✅見直したい習慣の例
- だらだら食べを控える
食べる時間が長くなると、口の中がずっと酸性状態に。これが虫歯の原因になります。 - タバコは歯ぐきの大敵
歯周病の進行を早めるだけでなく、治療しても治りにくくなることも。 - 睡眠不足・ストレスが多いと免疫力が落ちる
口の中の細菌バランスが乱れ、歯ぐきの炎症が起こりやすくなります。 - 食いしばりや歯ぎしりのクセに注意
気づかないうちに歯や骨に負担がかかっていることも。就寝中はマウスピースで予防できます。
こういった習慣を少し意識するだけでも、歯や歯ぐきを守る力がグンとアップします。
歯科医院で受けるプロフェッショナルケア
どれだけ丁寧に自分でケアしていても、どうしても落としきれない汚れや、気づかないうちに進んでいるトラブルもあります。
だからこそ、歯科医院での定期的なケアが欠かせません。
✅定期検診でできること
- 歯石・着色の除去(専用の器具で安全に除去)
- 歯ぐきのチェック(炎症の有無や出血の状態を確認)
- 虫歯・歯周病の早期発見
- 噛み合わせのチェック(ズレていないか、力が偏っていないか)
これらを定期的に確認することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
💡検診の目安:3〜6ヶ月に1回
さらに、必要に応じてフッ素塗布や、ブラッシング指導も受けられます。「自分では磨けているつもり」でも、プロに確認してもらうことで気づきがたくさんありますよ。
歯は、失ってしまってからでは元に戻せません。だからこそ、今ある歯を守ることが何より大切なんです。
9.インプラントは健康寿命を延ばすのに有効?
 しっかり噛める口を取り戻すことが、健康寿命を延ばす大きなカギになるんです。
しっかり噛める口を取り戻すことが、健康寿命を延ばす大きなカギになるんです。
特にインプラントは、「自分の歯のようにしっかり噛める」ことから、健康面でも多くのメリットがある治療法です。
インプラントで噛む力が回復するとどうなる?
歯を失うと、まず影響が出るのは「噛む力」。
入れ歯ではカバーしきれない場面もありますが、インプラントなら、天然の歯に近い力でしっかり噛めるようになります。
噛む力が回復すると、次のような良い変化が起こりやすくなります。
✅噛むことで脳が活性化
- 噛む刺激が脳に届き、記憶力や判断力の維持に役立ちます
- 認知症予防の観点からも注目されています
✅噛むことで体幹が安定しやすくなる
- 姿勢やバランス感覚にも関わってくるので、転倒リスクの軽減にもつながるといわれています
✅噛むことで表情や会話が豊かに
- 口元の筋肉が動くことで、笑顔や発音が自然に
- 人との会話が増え、外出する機会も増えていきます
つまり、インプラントによって噛む力を取り戻すことは、心と体の健康を取り戻すことにもつながるんですね。
食事の楽しみが戻ると、栄養バランスも変わってくる
「もう硬いものは諦めてる」
「いつも同じような食事になってしまう」
インプラントでしっかり噛めるようになると、これまで避けていた食べ物もまた楽しめるようになります。
✅噛めるようになると…
- 肉や野菜、繊維質のある食材もしっかり噛める
- 噛むことで唾液がよく出て、消化吸収もスムーズに
- 味や温度をしっかり感じられるようになり、食事そのものが楽しくなる
食事が楽しくなると、自然と食欲もわいてきます。
結果として、たんぱく質・ビタミン・ミネラルなどの栄養素をバランスよく摂れるようになり、体の元気が維持できるというわけです。
インプラントを長持ちさせるために大切なこと
インプラントは“埋めて終わり”ではありません。
天然の歯と同じように、ケアとメンテナンスを続けることで、長く快適に使える治療です。
✅インプラントを長く使うためのポイント
- 毎日の歯磨きと歯間ケアを丁寧に
インプラントの周りに歯垢がたまると、インプラント周囲炎の原因になります。 - 歯科医院での定期メンテナンスを欠かさない
3〜6ヶ月ごとに、噛み合わせ・清掃状態・歯ぐきの状態をチェック - 噛み合わせや歯ぎしりのチェックも大切
インプラントは強い力が加わりすぎるとダメージを受けることがあります。マウスピースなどでの対策も可能です。
インプラントは、きちんとケアすれば10年、20年と使えるケースも多くあります。
しっかり噛める状態を長く保つことが、健康寿命の延伸につながっていきます。
噛めることが、ただの“機能回復”ではなく、生活そのものを明るく、前向きに変えてくれるきっかけになります。
10.よくある質問
 最後に、患者様からよくいただくご質問をピックアップして、ひとつひとつお答えしていきます。ちょっとした疑問が、歯の健康を守るきっかけになるかもしれません。気になることがあれば、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。
最後に、患者様からよくいただくご質問をピックアップして、ひとつひとつお答えしていきます。ちょっとした疑問が、歯の健康を守るきっかけになるかもしれません。気になることがあれば、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。
Q1:「歯を失ったまま放置するとどうなるの?」
A1.これは非常によくあるご質問です。
「1本だけだから大丈夫かな…」「忙しくて、ついそのままにしている」
こういった方も多いのですが、実は歯を1本でも失ったままにしておくと、さまざまなリスクが出てきます。
✅放置することで起こりやすい問題
- 噛み合わせのバランスが崩れる
→ 周囲の歯が傾いたり、伸びたりして、他の歯にも負担がかかります - あごの骨が痩せる
→ 歯がなくなった部分は噛む刺激がなくなるため、骨が吸収されてしまいます - 発音がしにくくなる
→ 特に前歯を失った場合、「サ行」「タ行」などの発音に影響が出ることも - しっかり噛めないことで、消化や栄養バランスにも影響
→ 食べ物の制限が増え、柔らかいものに偏ってしまいがちに
このように、「たった1本」でも、放置することで全体の口腔バランスが崩れ、健康への影響がじわじわ出てくることがあるんです。
Q2:「健康寿命を延ばすには、インプラントと入れ歯どちらが良いの?」
A2.これは、患者様のライフスタイルやご希望によって変わってきます。
それぞれの特徴を簡単にまとめてみましょう。
✅インプラントの特徴
- 見た目も噛み心地も、天然歯に近い
- 噛む力がしっかり戻りやすい
- 他の歯に負担をかけない
- 骨がしっかりしていれば、10年以上長く使えるケースも
💡健康寿命との関係では、噛む力をしっかり取り戻すことで、認知症予防・転倒予防・食生活の質の向上など、トータルで見て大きなプラスになる治療です。
✅入れ歯の特徴
- 費用を抑えやすい
- 保険適用の範囲内で作れることが多い
- 外して洗えるので、お手入れしやすい
ただし、噛む力は天然歯やインプラントに比べて弱くなる傾向があり、装着時の違和感や、食事の制限を感じる方もいらっしゃいます。
💡ポイント
患者様にとって一番大事なのは、「無理なく、続けられること」。
迷ったときは、口の中の状態やご予算、ライフスタイルをもとに一緒に考えていくのがベストです。
Q3:「歯を守るために、今日からできることは?」
A3.これもとても多く聞かれるご質問です。
今すぐ始められること、意外とたくさんありますよ。
今日からできる5つのこと
- 朝と夜、1日2回しっかり磨く(できれば毎食後)
- デンタルフロスや歯間ブラシを取り入れる
- よく噛んで食べる(1口30回を目安に)
- だらだら食べを避け、食事の時間を意識する
- 3〜6ヶ月に1回は定期検診を受ける
この中で、「できそうなことから1つだけでも始めてみる」。
それだけでも、お口の中は大きく変わってきます。
また、すでに歯を失っている部分がある方は、「噛める状態に戻す治療」を早めに考えることが、これからの健康を守る第一歩になります。
毎日しっかり噛んで食べられること。
人と笑って話せること。
好きなものを味わえること。
そのどれもが、“健康で自分らしく生きる時間”=健康寿命をのばす力になります。
そしてそれを支えてくれるのが、「ご自身の歯」であり、「噛める口」なんです。
歯を失ってしまった方も、まだ元気にそろっている方も、
今できることをひとつずつ取り入れていけば、10年後・20年後の自分にしっかりつながっていきます。
「自分の歯を守りたい」「そろそろ口の健康も考えたい」そう思ったときは、ぜひお気軽にご相談ください。
“噛める幸せ”を未来まで続けるために、一緒にできることから始めていきましょう。
群馬県高崎市のインプラント治療専門
『加藤デンタルオフィス高崎』
群馬県高崎市八島町273 高崎ピュアビル4階
TEL:027-388-0851
*監修者
*経歴
樹徳高等学校卒業。日本歯科大学 新潟歯学部卒業。
医療法人社団 朋優会 ソフィア歯科インプラントセンター 分院長
医療法人MSO かとう歯科 理事長・院長
*所属学会・研究会
・日本顎咬合学会 認定医
・国際口腔インプラント学会(ISOI)ドイツ口腔インプラント学会 認定医
・国際口腔インプラント協会(IDIA)認定医・専門医・指導医
・インディアナ大学医学部解剖学 認定医
・インディアナ大学 インプラント研究員
・日本インプラント学会 会員
・日本歯周病学会 会員
詳しいプロフィールはこちらより