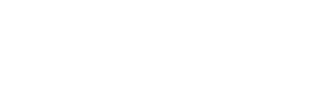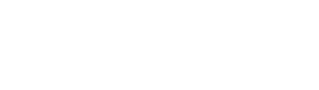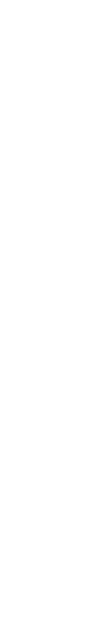NEWS
お知らせ
2025.03.13 |
インプラントが顎の骨を守る?その理由と関係性とは? |
2025.03.13
インプラントが顎の骨を守る?その理由と関係性とは?
こんにちは。加藤デンタルオフィス高崎です。
歯を失ったまま放置していると、顎の骨は 少しずつ痩せてしまう ことをご存じでしょうか?噛む力が骨に伝わらなくなることで、 骨の吸収が進み、顔の輪郭や噛み合わせにも影響 を与える可能性があります。
そんな中で 「インプラントが顎の骨を守る」 という話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?実は、インプラントは 顎の骨にしっかりと固定されることで、骨の吸収を防ぎ、健康な噛み合わせを維持する役割 を果たします。しかし、 治療方法やメンテナンスを間違えると、顎の健康に悪影響を及ぼす こともあるため、慎重に選ぶことが大切です。
今回は、 「インプラントと顎の健康の関係」 や 「顎の骨を守るために気をつけるべきポイント」 について解説していきます。インプラントを検討している方も、すでに治療を受けた方も、 大切な顎の健康を守るために知っておきたい情報 をチェックしてみましょう!
1.こんなお悩みありませんか?
 歯を失った後、顎の骨の健康や噛み合わせの変化について心配される患者様は少なくありません。
歯を失った後、顎の骨の健康や噛み合わせの変化について心配される患者様は少なくありません。
・「歯を失うと顎の骨が痩せるって本当?」
・「インプラントを入れると、顎の健康にどんな影響があるの?」
・「噛み合わせが変わることで、顎が痛くなったりしない?」
このようなお悩みをお持ちの方に向けて、インプラント治療と顎の健康の関係について、お話ししていきます。
インプラントは、単に「歯を補うためのもの」ではありません。正しく機能することで、顎の骨を守り、噛み合わせを安定させる効果も期待できるのです。
2.インプラントと顎の健康の関係とは?
 インプラント治療は、歯を補うだけでなく、顎の骨を守る役割も果たします。歯を失ったままにしておくと、顎の骨が痩せる(吸収される)ことがありますが、インプラントを適切に埋入することで、そのリスクを軽減できます。
インプラント治療は、歯を補うだけでなく、顎の骨を守る役割も果たします。歯を失ったままにしておくと、顎の骨が痩せる(吸収される)ことがありますが、インプラントを適切に埋入することで、そのリスクを軽減できます。
インプラントが顎の骨に与える影響
歯があるときは、噛む力が顎の骨に伝わり、骨が健康な状態を維持できます。しかし、歯を失うとその刺激がなくなり、骨が徐々に痩せてしまうのです。これを防ぐために、インプラントが大きな役割を果たします。
顎の骨が痩せるメカニズム
歯を失った後、以下のようなメカニズムで顎の骨が痩せていきます。
✅ 刺激不足による骨吸収
歯があるときは、噛む力が顎の骨に伝わり、骨の新陳代謝が活発に行われます。しかし、歯が抜けると刺激がなくなり、骨の再生が追いつかず、徐々に骨が減少してしまうのです。
✅ 時間が経つほど骨が減る
歯を失ってすぐの段階では目立った変化はありませんが、数カ月~数年経つと、顎の骨が大きく減少することがあります。顎の骨が痩せると、顔の輪郭が変わったり、他の歯に負担がかかったりする可能性もあります。
✅ 噛み合わせのズレが発生する
顎の骨が減ると、隣の歯が倒れたり、噛み合わせが変わったりして、顎関節に負担がかかることがあります。その結果、顎の痛みや噛みづらさを引き起こすことも。
インプラントが顎の骨を守る仕組み
インプラントは、天然の歯の根の代わりとなるチタン製の人工歯根を顎の骨に埋め込む治療です。これにより、噛むたびに顎の骨に適度な刺激が伝わり、骨の吸収を抑えることができます。
🔹 天然の歯と同じように刺激を伝える
インプラントは、しっかりと顎の骨に固定されるため、食事の際に噛む力が骨に伝わりやすくなります。この刺激があることで、顎の骨の新陳代謝が促進され、健康な骨の状態を維持しやすくなるのです。
🔹 骨吸収を抑えて見た目もキープ
インプラントを入れることで、顎の骨が痩せるのを防ぐだけでなく、顔の輪郭を保つ効果も期待できます。骨が減ると、口元がやせた印象になったり、ほうれい線が深くなったりすることがありますが、インプラントによってそのリスクを抑えられます。
🔹 噛み合わせを整えて顎の負担を軽減
インプラントを適切に埋入すると、噛み合わせのバランスが取れ、顎関節や周囲の筋肉への負担が軽減されます。これにより、顎関節症のリスクを低減し、快適な噛み心地を長く維持できるのです。
歯を失うと顎の骨が痩せてしまうリスクがありますが、インプラントを入れることで、そのリスクを軽減できます。インプラントは「ただの人工の歯」ではなく、顎の健康を維持するための大切な役割を担っているのです。
3.歯を失うと顎の骨がどうなる?
 歯を失った後、そのまま放置してしまうと、顎の骨が痩せてしまうことをご存じでしょうか?これは「骨吸収」と呼ばれる現象で、放置すると噛み合わせの変化や、見た目の変化につながることがあります。
歯を失った後、そのまま放置してしまうと、顎の骨が痩せてしまうことをご存じでしょうか?これは「骨吸収」と呼ばれる現象で、放置すると噛み合わせの変化や、見た目の変化につながることがあります。
顎の骨が痩せる原因
歯を失うと、その部分の骨に噛む刺激が伝わらなくなり、骨の新陳代謝が低下します。その結果、次第に骨が吸収されてしまうのです。
✅ 噛む力が顎の骨に伝わらなくなる
・歯があるときは、食べ物を噛むたびに顎の骨が適度に刺激され、新しい骨が作られる仕組みになっています。
・しかし、歯が抜けると、その刺激がなくなり、骨の吸収が進みやすくなるのです。
✅ 時間とともに進行する骨吸収
・歯を失ってすぐに骨が痩せるわけではありませんが、数カ月~数年経つと、骨のボリュームが減少していきます。
・特に抜歯後1年以内がもっとも骨が減少しやすい時期とされています。
✅ 入れ歯やブリッジでは防げない
・入れ歯やブリッジは顎の骨を支える働きがないため、骨吸収を完全に防ぐことはできません。
・入れ歯は歯ぐきの上に乗せるだけなので、噛む刺激が直接骨に伝わりません。
・ブリッジも、周囲の歯を支えにするため、抜けた部分の骨は使われず、徐々に痩せていくことがあります。
骨の吸収が進むとどうなる?
顎の骨が痩せると、さまざまな問題が発生します。
🔹 噛み合わせのバランスが崩れる
・歯が抜けた部分の骨が減ると、隣の歯や噛み合う歯が移動してしまい、噛み合わせが変わることがあります。
・これにより、顎関節に負担がかかり、顎の痛みや違和感が出る可能性もあります。
🔹 顔の輪郭が変わる
・顎の骨が減少すると、口元のボリュームがなくなり、老けた印象になることがあります。
・特に下顎の骨が減ると、ほうれい線が深くなったり、口元がくぼんで見えることがあります。
🔹 インプラント治療が難しくなる
・骨が十分にあるうちにインプラントを埋入するのが理想的ですが、骨が減ってしまうと、インプラントを支えるだけの骨が足りなくなってしまうことがあります。
・この場合、骨造成(骨を増やす手術)を行う必要があり、治療期間が長くなることがあります。
インプラント以外の選択肢との比較
歯を失ったときの治療法には、インプラント、ブリッジ、入れ歯の3つが代表的ですが、
それぞれ顎の骨への影響が異なります。
| 治療法 | 顎の骨への影響 | メリット | デメリット |
| インプラント | 骨に直接固定するため、骨吸収を防ぐ | 骨の健康を維持しやすい / 天然歯に近い噛み心地 | 外科手術が必要 / 費用が高い |
| ブリッジ | 失った歯の部分の骨は徐々に減少 | 手術不要 / 比較的短期間で治療可能 | 支えにする歯に負担がかかる / 骨吸収を防げない |
| 入れ歯 | 顎の骨を支える力がないため骨吸収が進行 | 取り外しできる / 比較的安価 | 噛む力が弱い / 違和感がある / 骨の減少で合わなくなる |
こうして比較すると、顎の骨を守るためにはインプラントが最も適していることが分かります。
歯を失うと、噛む力が伝わらなくなることで顎の骨が痩せてしまう可能性があります。これは見た目だけでなく、噛み合わせや健康にも影響を及ぼす重要な問題です。
4.インプラントは顎の骨を守る?
 歯を失うと、噛む刺激が伝わらなくなり、顎の骨が少しずつ痩せてしまうことがあります。これは「骨吸収」と呼ばれる現象で、放置すると見た目の変化や噛み合わせの乱れにつながる可能性があります。では、インプラント治療を行うことで、顎の骨を守ることができるのでしょうか?
歯を失うと、噛む刺激が伝わらなくなり、顎の骨が少しずつ痩せてしまうことがあります。これは「骨吸収」と呼ばれる現象で、放置すると見た目の変化や噛み合わせの乱れにつながる可能性があります。では、インプラント治療を行うことで、顎の骨を守ることができるのでしょうか?
インプラントが骨吸収を防ぐ仕組み
インプラントが顎の骨を健康に保つ最大の理由は、「噛む刺激を骨に直接伝えられること」です。
✅ 天然歯と同じように骨に力をかけられる
・天然の歯根は、噛むたびに顎の骨に適度な刺激を与え、新しい骨が作られるサイクルを維持します。
・インプラントは人工の歯根を顎の骨に埋め込むため、噛む刺激が骨に伝わり、骨の健康が保たれます。
✅ 骨吸収の進行を防ぐ
・歯を失った部分を放置すると、その部分の骨は使われなくなり、徐々に吸収されてしまいます。
・インプラントが埋め込まれることで、骨がしっかりと機能し続けるため、骨吸収のリスクが大幅に減少します。
✅ 安定した噛み合わせを維持できる
・骨が減ると、周囲の歯が傾いたり、噛み合わせがズレたりすることがあります。
・インプラントを入れることで、噛む力が均等に分散され、他の歯や顎関節への負担も軽減されます。
インプラントを長持ちさせるためのポイント
せっかくインプラントを入れたなら、できるだけ長く快適に使いたいですよね。インプラントは、適切なケアと定期的なメンテナンスを行うことで、10年以上、場合によっては一生使い続けることも可能です。
✅ 正しいオーラルケアを続ける
・インプラントは虫歯にはなりませんが、**インプラント周囲炎(歯周病のような炎症)**になるリスクがあります。
・毎日のブラッシングや歯間ブラシ・デンタルフロスを使って、しっかりと汚れを取り除きましょう。
✅ 定期的なメンテナンスを受ける
・インプラントを長持ちさせるためには、3~6カ月ごとの定期検診が重要です。
・歯科医院での専門的なクリーニングを受けることで、インプラント周囲炎のリスクを低減できます。
✅ 噛み合わせの変化をチェックする
・噛み合わせが変化すると、インプラントに過剰な負担がかかり、トラブルの原因になることがあります。
・違和感を感じたら、早めに歯科医院に相談しましょう。
✅ 健康的な生活習慣を心がける
・喫煙はインプラント周囲炎のリスクを高めるため、できるだけ禁煙するのがおすすめです。
・栄養バランスの取れた食事を意識し、骨の健康を維持するためにカルシウムやビタミンDをしっかり摂取しましょう。
インプラント治療は、噛む力を回復させるだけでなく、顎の骨を守るためにも重要な治療法です。歯を失ったままにしておくと、骨吸収が進み、噛み合わせの変化や見た目の変化につながる可能性があります。しかし、インプラントを埋め込むことで、骨に適度な刺激を与え、骨の健康を維持することが可能になります。
5.噛み合わせと顎のバランス
 インプラント治療を受ける際に、「噛み合わせの変化が顎に影響しないか?」と心配される患者様は少なくありません。実際に、噛み合わせが悪いと顎のバランスが崩れ、痛みや違和感、さらには顎関節症を引き起こす可能性もあります。
インプラント治療を受ける際に、「噛み合わせの変化が顎に影響しないか?」と心配される患者様は少なくありません。実際に、噛み合わせが悪いと顎のバランスが崩れ、痛みや違和感、さらには顎関節症を引き起こす可能性もあります。
噛み合わせの変化が顎の健康に与える影響
歯は単に「噛む」ためのものではなく、顎の骨や筋肉、関節とバランスを取りながら機能しています。そのため、噛み合わせが乱れると、顎への負担が増し、さまざまなトラブルにつながることがあります。
✅ 噛み合わせが乱れると…
・顎の筋肉に余計な負担がかかる
・左右のバランスが崩れ、顎の関節に負担がかかる
・顎関節症(口を開けにくい、カクカク音がする、痛みがある)を引き起こす
・頭痛や肩こり、首のこりが悪化する
例えば、歯を失ったまま放置すると、周りの歯が傾いたり、反対側の歯が伸びてきたりして、噛み合わせが崩れてしまいます。また、入れ歯やブリッジでは、十分な噛む力が得られず、片側ばかりで噛む癖がついてしまうこともあります。
インプラント治療では、失った歯の代わりに人工歯根を埋め込むため、自然な噛み合わせを再現しやすいのが特徴です。しかし、治療後の噛み合わせ調整を適切に行わなければ、顎のバランスを崩してしまう可能性があるため、慎重に調整する必要があります。
インプラント後の噛み合わせ調整の重要性
✅噛み合わせの調整をしないと…
・インプラントの上部構造(人工歯)に過度な負担がかかり、破損や脱落のリスクが高まる
・周囲の天然歯にも余計な力が加わり、歯が痛んだり、すり減ったりする
・顎関節に負担がかかり、顎の痛みや違和感を感じることがある
そのため、インプラント治療後には、噛み合わせの微調整を行うことが非常に重要です。歯科医院では、患者様の噛み合わせを確認しながら、必要に応じて噛み合わせの高さや角度を調整していきます。
🦷 噛み合わせ調整の流れ
1. 仮歯で噛み合わせを確認:インプラントを埋めた後、仮歯を装着し、噛み合わせのバランスをチェックします。
2. 最適な高さや角度を調整:周囲の歯や顎の動きに合わせて、人工歯の形を調整します。
3. 定期的なメンテナンスで微調整:噛み合わせは時間とともに変化するため、定期的なチェックを行いながら調整します。
特に、噛む力が強い方や歯ぎしりの癖がある方は、噛み合わせの調整を怠ると、インプラントが割れたり、周囲の歯にダメージを与えることがあります。そのため、定期的なメンテナンスで、噛み合わせの変化を早めに察知し、適切な対応をすることが大切です。
顎関節症とインプラントの関係
顎関節症は、「口を開けるとカクカク音がする」「顎が痛む」「口が開きづらい」などの症状が出る疾患です。噛み合わせの乱れや、顎にかかる過度な負担が原因となることが多く、放置すると症状が悪化する可能性があります。
✅ 顎関節症の原因となる要素
・歯を失ったまま放置し、噛み合わせが崩れる
・入れ歯やブリッジが合わず、片側だけで噛む癖がつく
・ストレスや緊張で無意識に歯を食いしばる
・寝ている間の歯ぎしりや食いしばり
インプラント治療は、適切な噛み合わせを再構築できるため、顎関節症のリスクを軽減する効果も期待できます。
ただし、インプラントが適切に埋め込まれていなかったり、噛み合わせの調整が不十分だったりすると、逆に顎関節症を悪化させる可能性もあるため、注意が必要です。
💡 顎関節症を防ぐためのポイント
✅ 治療前のカウンセリングをしっかり行う
・噛み合わせのチェックを入念に行い、治療計画を慎重に立てる
✅ インプラント治療後も定期的に噛み合わせを調整
・噛み合わせが少しでもズレていると感じたら、早めに歯科医院で診てもらう
✅ 歯ぎしり・食いしばり対策をする
・マウスピースを使用し、インプラントや顎への負担を軽減する
インプラント治療を成功させるためには、噛み合わせと顎のバランスをしっかり整えることが欠かせません。噛み合わせが乱れると、顎の筋肉や関節に負担がかかり、顎の痛みや違和感、さらには顎関節症を引き起こす可能性があります。
6.インプラント治療の流れと顎の状態チェック
 インプラント治療を成功させるためには、顎の骨の状態をしっかりと確認することがとても重要です。顎の骨が十分にあるかどうかは、インプラントの安定性や長持ちするかどうかに大きく関わります。そのため、治療の前に詳しい診断を行い、必要があれば骨を増やす処置も検討することが大切です。
インプラント治療を成功させるためには、顎の骨の状態をしっかりと確認することがとても重要です。顎の骨が十分にあるかどうかは、インプラントの安定性や長持ちするかどうかに大きく関わります。そのため、治療の前に詳しい診断を行い、必要があれば骨を増やす処置も検討することが大切です。
インプラント前の顎の状態診断
✅ 顎の骨の厚みと高さの確認
インプラントは、顎の骨の中に人工歯根を埋め込む治療です。そのため、顎の骨の厚みや高さが十分にないと、インプラントが安定せず、長持ちしにくくなります。
特に、歯を失ってから長期間放置していると、顎の骨がどんどん痩せてしまい、インプラントを支える土台が不十分になることがあります。
✅ 骨の質(密度)のチェック
骨は単に「ある・ない」だけでなく、骨の密度(硬さ)も重要なポイントです。骨密度が低いと、インプラントがしっかり固定されず、治療の成功率が下がる可能性があります。
✅ 顎の形や神経の位置の確認
下顎には大きな神経(下歯槽神経)が通っているため、インプラントを埋める際に神経に触れないよう注意が必要です。
上顎の場合は、副鼻腔(空洞)があるため、骨の高さが足りないとインプラントを埋め込むスペースが確保できないこともあります。
CT撮影での骨密度チェック
インプラント治療では、CT(3Dレントゲン)を使って顎の状態を詳しく確認します。
✅ CT検査でわかること
🔹 顎の骨の厚みと高さ
🔹 骨密度(インプラントがしっかり固定できるか)
🔹 神経や血管の位置(安全に治療できるか)
🔹 副鼻腔の状態(上顎にインプラントを埋めるスペースがあるか)
CT撮影は、通常のレントゲンよりも詳細な情報を得ることができ、より安全で確実なインプラント治療を行うために欠かせない検査です。
特に、骨が痩せているかどうかは、見た目だけではわからないため、CT画像を見ながらしっかり診断することが大切です。
顎の骨が足りない場合の治療法(骨造成など)
「顎の骨が足りないと言われたけど、インプラントはできないの?」
そんな不安を抱える患者様も多いかもしれません。実は、骨が不足している場合でも、骨を増やす処置を行うことでインプラント治療が可能になるケースがほとんどです。
✅ 骨を増やす治療法(骨造成)
骨が足りない場合には、以下の方法で骨を補強し、インプラントがしっかり固定できる環境を整えます。
🔹 ソケットリフト(上顎の骨を増やす)
– 上顎の骨が薄い場合に行う処置
– 副鼻腔の底を少し持ち上げて、人工の骨を入れる
– これにより、インプラントを埋め込むための十分な骨を確保できる
🔹 サイナスリフト(大きく骨を増やす)
– 上顎の骨の高さが大幅に足りない場合に行う処置
– 側面からアプローチし、人工の骨を移植
– 治療期間はやや長めだが、高い成功率が期待できる
🔹 GBR(骨誘導再生法)
– 骨の厚みや幅が足りない場合に行う処置
– 骨の不足している部分に人工の骨を補填し、数ヶ月かけて骨の再生を促す
– インプラントと併用することが多い
🔹 自家骨移植
– 自分の骨を別の部位から採取して移植する方法
– 一般的に、顎の奥や腰の骨から採取
– 自家骨なので定着しやすいが、採取部分の負担がある
骨が足りないからといって諦めないで!
「骨が少ないと言われたら、インプラントは無理なの?」と心配になる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、現在のインプラント治療は進歩しており、骨が少ない場合でも適切な処置を行うことでインプラント治療が可能になります。
🦷 インプラント治療の選択肢が広がるポイント
✔事前にCT検査を行い、骨の状態を正確に診断
✔必要に応じて骨造成を行い、インプラントを支える土台を作る
✔患者様に合った最適な治療計画を立てる
「骨が足りないから無理」と諦めず、まずは歯科医院で詳しく診てもらうことが大切です!
インプラント治療では、顎の骨の状態がとても重要です。
「自分の顎の骨の状態が気になる…」「インプラントを考えているけど不安がある…」
そんな方は、ぜひ一度歯科医院でご相談ください。
7.顎の健康を維持するためのポイント
 インプラント治療を成功させるためには、手術が終わった後のケアがとても大切です。インプラントは、天然の歯と同じようにしっかり噛める素晴らしい治療法ですが、適切なメンテナンスをしないとトラブルにつながる可能性もあります。また、顎の骨を健康に保つためには、日々の食事や生活習慣も重要です。
インプラント治療を成功させるためには、手術が終わった後のケアがとても大切です。インプラントは、天然の歯と同じようにしっかり噛める素晴らしい治療法ですが、適切なメンテナンスをしないとトラブルにつながる可能性もあります。また、顎の骨を健康に保つためには、日々の食事や生活習慣も重要です。
インプラント後の正しいメンテナンス
インプラントを長く快適に使うためには、適切なメンテナンスが欠かせません。天然の歯とは違い、インプラント自体はむし歯にはなりませんが、歯周病のような「インプラント周囲炎」になるリスクがあります。
✅ 日々のセルフケア
🔹 歯磨きは丁寧に!
– 柔らかめの歯ブラシを使い、インプラントと歯ぐきの境目をしっかり磨く
– フロスや歯間ブラシを使って、隙間の汚れもきちんと落とす
– 抗菌作用のあるマウスウォッシュを併用するとさらに効果的
🔹 歯科医院での定期メンテナンス
– 3~6ヶ月ごとの定期検診を受け、インプラントや周囲の骨の状態をチェック
– 専門のクリーニング(PMTC)を受けて、普段のケアでは落とせない汚れを除去
– 噛み合わせの確認を行い、インプラントに余計な負担がかかっていないかチェック
食事や生活習慣で顎の骨を守る方法
インプラントがしっかりと顎の骨に定着し、長く健康な状態を保つためには、骨の健康を維持することが大切です。特に、食事や生活習慣は顎の骨に大きく影響します。
✅ 骨を強くする食べ物を意識する
骨の健康に必要な栄養素をしっかり摂ることで、インプラントを支える顎の骨を丈夫に保つことができます。
🔹 カルシウム(骨を強くする)
– 牛乳、チーズ、ヨーグルト
– 小魚、豆腐、納豆
🔹 ビタミンD(カルシウムの吸収を助ける)
– 鮭、いわし、きのこ類
🔹 ビタミンK(骨の形成をサポート)
– ほうれん草、ブロッコリー、納豆
🔹 タンパク質(骨の材料となる)
– 鶏肉、卵、大豆製品
また、過度なアルコール摂取や喫煙は、インプラントの定着を妨げ、骨を弱くする原因になります。特に喫煙は、血流を悪くし、骨の再生を遅らせるため、インプラントを長持ちさせるためにも禁煙をおすすめします。
適切な噛み合わせを保つためのセルフケア
インプラントは、しっかりと噛めるようになる素晴らしい治療法ですが、噛み合わせが悪いと顎に余計な負担がかかり、トラブルの原因になることがあります。
✅ 噛み合わせのチェック方法
インプラント治療後、次のような症状がある場合は、噛み合わせに問題がある可能性があります。
🔹 噛んだときに違和感や痛みがある
🔹 顎の関節がカクカクする、開け閉めで音がする
🔹 朝起きたときに顎が疲れている
🔹 片側の歯だけで噛む癖がある
こうした症状がある場合は、早めに歯科医院で相談し、必要に応じて噛み合わせを調整してもらいましょう。
✅ セルフケアでできること
🔹 左右均等に噛む
– 片側だけで噛むと、噛み合わせのバランスが崩れ、顎に負担がかかります
🔹 食べるときによく噛む
– 柔らかいものばかり食べていると、顎の筋肉が衰え、噛み合わせが悪くなることがあります
🔹 歯ぎしり・食いしばりに注意
– 歯ぎしりや食いしばりは、インプラントに強い負荷をかけてしまうため、マウスピースを使うなどの対策が必要です
治療後のメンテナンスや生活習慣を見直して、健康な顎を維持しましょう!
8.インプラント治療後の注意点
 インプラント治療を受けた後は、長く快適に使い続けるためのケアと注意点がいくつかあります。特に顎に負担をかけない習慣や、インプラント周囲炎の予防、定期的なメンテナンスが重要です。
インプラント治療を受けた後は、長く快適に使い続けるためのケアと注意点がいくつかあります。特に顎に負担をかけない習慣や、インプラント周囲炎の予防、定期的なメンテナンスが重要です。
顎に負担をかけないための習慣
インプラントは強度があり、しっかり噛むことができますが、無理な力がかかると顎やインプラント自体に負担がかかることがあります。日常生活の中で、顎に優しい習慣を意識することが大切です。
✅ 噛み合わせのバランスを意識する
- 片側だけで噛まないようにする(左右均等に使うことが大事!)
- 硬すぎるものを無理に噛まない(氷、飴、ナッツ類など)
- 長時間の歯の食いしばりに注意(無意識に力が入っていることも)
✅ 食いしばりや歯ぎしりの対策をする
- 寝ている間の歯ぎしりが気になる方は、マウスピースを活用
- 日中、緊張すると歯を食いしばる癖がある方は意識してリラックス
- ストレス管理も大切!適度な運動やリラックスする時間をとる
✅ 正しい姿勢を保つ
- スマホやパソコンの画面を見続けると、無意識に顎に負担がかかる
- 猫背を避け、顎や首に負担のかからない姿勢を意識する
- 肩や首のストレッチを取り入れ、血流を良くする
インプラント周囲炎を防ぐケア
インプラントはむし歯にはなりませんが、**インプラント周囲炎(インプラントの周りに起こる歯周病のような炎症)**には注意が必要です。インプラント周囲炎を防ぐために、毎日の口腔ケアをしっかり行いましょう。
✅ 正しい歯磨きの習慣をつける
- 柔らかめの歯ブラシを使い、歯ぐきに優しいブラッシングをする
- インプラントと歯ぐきの境目を特に丁寧に磨く
- フロスや歯間ブラシで、歯と歯の間の汚れも落とす
✅ 洗口液を活用する
- 抗菌作用のあるマウスウォッシュを取り入れると、細菌の繁殖を抑えられる
- アルコールが強いものは口の乾燥を招くこともあるため、刺激の少ないものを選ぶ
✅ 舌の汚れにも気をつける
- 舌の表面にたまる汚れ(舌苔)も、口臭や細菌繁殖の原因になる
- 専用の舌ブラシや舌クリーナーを使って、軽くケアする
定期的なメンテナンスの重要性
インプラントを長く健康に使い続けるためには、歯科医院での定期メンテナンスが不可欠です。毎日のセルフケアだけでは落としきれない汚れが蓄積したり、噛み合わせが少しずつ変化したりすることがあるため、定期的なチェックが大切です。
✅ 定期検診のスケジュール
- 3~6ヶ月ごとに歯科医院でメンテナンスを受ける
- インプラント周囲の歯ぐきや骨の状態を確認する
- 噛み合わせの調整を行い、顎への負担を防ぐ
✅ 歯科医院でのクリーニング(PMTC)
- 家庭の歯磨きでは落としきれない歯石を専門の器具で除去
- インプラントの表面を傷つけないよう、専用のクリーニング方法でケア
- 定期的なクリーニングを受けることで、インプラント周囲炎のリスクを軽減
インプラント治療後の注意点をしっかり守ることで、インプラントを長持ちさせ、顎の健康を維持することができます。
9.顎の健康を考えたインプラントの選び方
 インプラント治療を受ける際に、「どんなインプラントを選ぶべきか?」「顎の骨の状態に合った治療方法は?」と悩まれる方も多いでしょう。インプラントは種類や治療方法によって、顎の健康への影響が異なります。
インプラント治療を受ける際に、「どんなインプラントを選ぶべきか?」「顎の骨の状態に合った治療方法は?」と悩まれる方も多いでしょう。インプラントは種類や治療方法によって、顎の健康への影響が異なります。
インプラントの種類と特徴
インプラントにはいくつかの種類があり、患者様の顎の骨の状態や噛み合わせ、希望する治療期間によって最適なものが異なります。代表的なインプラントの種類を見ていきましょう。
✅ スタンダードなインプラント
- 特徴:一般的に使用される最も標準的なタイプ。チタン製のインプラント体を顎の骨に埋め込み、上部に人工歯を装着します。
- 適したケース:顎の骨の厚みや高さが十分にある方。
- メリット:長期的に安定し、自然な噛み心地を実現。
✅ ショートインプラント
- 特徴:通常のインプラントより短いタイプ。顎の骨の高さが不足している場合に適用されます。
- 適したケース:骨移植を避けたい方、顎の骨が薄い方。
- メリット:手術が比較的シンプルで、治療期間が短縮できることも。
✅ オールオン4(All-on-4)
- 特徴:片顎4本のインプラントで人工歯を固定する治療法。
- 適したケース:総入れ歯の方、複数の歯を失っている方。
- メリット:少ない本数のインプラントで、短期間でしっかり噛める状態に。
✅ ザイゴマインプラント
- 特徴:通常のインプラントでは埋め込めないほど顎の骨が少ない方に適用されるインプラント。
- 適したケース:骨が極端に少ない方、通常のインプラントが難しい方。
- メリット:骨移植なしで治療可能な場合がある。
患者様の顎の状態に合わせて、どのインプラントが適しているのかを見極めることが重要です。
顎の骨の状態に合わせた治療方法
インプラント治療を成功させるためには、顎の骨の健康状態をしっかり診断し、それに合った治療計画を立てることが欠かせません。
✅ 顎の骨の状態をチェックする方法
- CTスキャンを活用し、骨の厚みや密度を精密に検査する
- 歯周病の影響で骨が減っていないかを確認する
- 噛み合わせや顎関節のバランスを診断する
✅ 顎の骨が足りない場合の対処法
顎の骨が少ない場合、そのままインプラントを埋め込むと安定性が悪く、長持ちしないリスクがあります。そのため、以下のような治療が選択肢に入ります。
- 骨造成(GBR法):人工骨や自己骨を移植し、骨の再生を促す治療。
- ソケットリフト:上顎の骨が薄い場合に、上顎洞(サイナス)を押し上げて骨を補填する方法。
- スプリットクレスト:顎の骨が薄い部分を拡げて、インプラントを埋め込むスペースを作る方法。
患者様一人ひとりの骨の状態に合わせた治療計画を立てることが、インプラントを長持ちさせるポイントになります。
インプラント専門医の選び方
インプラント治療は、専門的な知識と技術が必要な治療です。信頼できる歯科医師を選ぶことで、より安心して治療を受けることができます。
✅ インプラント専門医を選ぶ際のポイント
- 経験と実績が豊富か?
- インプラントの症例数が多いか(実績のある歯科医院を選ぶ)
- 難症例にも対応しているか(骨が少ないケースにも対応できる技術力があるか)
- CT撮影やシミュレーションができる設備が整っているか?
- 3DのCT画像で精密な診断をしてもらえるか(骨の状態をしっかり把握する)
- デジタルシミュレーションで噛み合わせやインプラントの位置を決めるか
- アフターケア・メンテナンスが充実しているか?
- インプラントを長持ちさせるには、定期的なメンテナンスが必須です。
- 治療後も定期的な検診を受けられる体制が整っている歯科医院を選びましょう。
- カウンセリングが丁寧か?
- インプラント治療に対する不安や疑問に、納得できるまで説明してくれるかが重要。
- 無理に治療を勧める医院ではなく、患者様の状態に合った最適な治療法を提案する医院が安心。
インプラント治療は、適切な種類を選び、顎の骨の状態を考慮した上で計画的に進めることが大切です。
10.よくある質問
 インプラント治療を考える際、「顎の健康に影響はないのか?」と気になる方も多いでしょう。顎の骨や噛み合わせの状態によって、治療後の影響が異なるため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
インプラント治療を考える際、「顎の健康に影響はないのか?」と気になる方も多いでしょう。顎の骨や噛み合わせの状態によって、治療後の影響が異なるため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
Q1.インプラントが顎関節症を引き起こすことはある?
A1. 基本的にはありませんが、噛み合わせが合っていないと顎に負担がかかる可能性があります。
インプラント自体が顎関節症の原因になることはありません。しかし、インプラントを埋めた後の噛み合わせが不適切だと、顎に余計な負担がかかることがあり、結果的に顎関節症の症状を引き起こす可能性があります。
⚠️ こんな症状が出たら要注意!
- 口を開け閉めするとカクカク音がする
- 顎が疲れやすい、痛みがある
- 朝起きたときに顎がこわばる
🔹 予防策
- 経験豊富な歯科医師に噛み合わせをしっかり調整してもらう
- インプラント装着後も、定期的に噛み合わせのチェックを受ける
- 必要に応じてナイトガード(マウスピース)を使用する
噛み合わせが原因で顎関節に負担がかかることを防ぐため、定期的なメンテナンスがとても大切です。
Q2.インプラントは骨粗鬆症の人でも可能?
A2. 骨の状態をしっかりチェックすれば、骨粗鬆症の方でもインプラント治療ができるケースはあります。
骨粗鬆症とは骨がスカスカになり、骨折しやすくなる病気です。インプラントは顎の骨に直接埋め込む治療なので、「骨粗鬆症でも大丈夫?」と不安に思われる方も多いでしょう。
🔹 インプラント治療を受ける前のポイント
- まずはCT撮影で骨密度をチェックし、インプラントが可能か判断する。
- 骨が弱くなっている場合は、骨造成(GBR法)やソケットリフトなどの治療を併用することで対応できることが多い。
- 骨粗鬆症の治療薬を服用している場合、インプラントとの相性を事前に確認する必要がある。
🔸 注意が必要なケース
特に「ビスフォスフォネート系薬剤(骨粗鬆症の治療薬)」を長期間服用している場合は、顎の骨の血流が悪くなり、骨が治りにくくなるリスクがあります。このような場合は、主治医や歯科医とよく相談し、慎重に治療計画を立てることが大切です。
Q3.顎の骨が薄い場合でもインプラントはできる?
A3. 顎の骨が薄い場合でも、骨を補う治療法を併用すればインプラントが可能です。
インプラントを埋め込むには、ある程度の骨の厚みと高さが必要です。しかし、長期間歯を失ったままでいると、顎の骨が徐々に痩せていくため、「骨が足りなくてインプラントができない」と言われることもあります。
🔹 骨が足りない場合の治療法
- GBR法(骨造成)
- 人工骨や自家骨を使い、不足した骨を再生させる治療法。
- 比較的多くのケースで行われ、骨の再生に3〜6ヶ月ほどかかる。
- ソケットリフト(上顎洞挙上術)
- 上顎の骨が薄い場合に、骨の高さを増やす方法。
- インプラントと同時に手術を行うことも可能。
- ショートインプラント
- 通常のインプラントよりも短いタイプのインプラントを使用することで、骨造成をせずに済むケースも。
顎の骨が薄くても、骨を増やす治療を組み合わせることで、インプラント治療が可能な場合が多いため、まずは専門医に相談しましょう。
Q4.治療後、噛み合わせが変わることはある?
A4. 適切な調整を行えば、噛み合わせが大きく変わることはありません。
インプラント治療後、噛み合わせが変わったように感じることがあります。これは、今まで歯がなかった部分にしっかり噛める人工歯が入るため、口の中のバランスが変わるためです。
🔹 噛み合わせの変化が起こる原因
- インプラントの高さが合っていない → 調整すれば解決可能
- 歯の位置が変わることで、噛み癖が変わる → 数週間〜数ヶ月で慣れる
- 長年噛み合わせが乱れていた場合 → 他の歯の治療が必要なことも
🔸 インプラント後に噛み合わせを安定させるポイント
- 治療後1〜3ヶ月間は、定期的に噛み合わせをチェックする
- 歯ぎしりや食いしばりがある場合は、ナイトガード(マウスピース)を使用する
- 必要に応じて、噛み合わせの微調整を行う
インプラントはしっかりとした噛み合わせを回復させる治療なので、適切な調整をすれば、長期的に快適に噛めるようになります。
インプラント治療は、単に「失った歯を補う」だけでなく、顎の健康を守るためにも非常に重要な治療です。歯を失ったままにすると、顎の骨が徐々に痩せ、噛み合わせのバランスが崩れることで、全身の健康にも影響を及ぼす可能性があります。しかし、インプラントを適切に活用することで、顎の骨を健康に保ち、しっかりと噛める状態を長く維持することが可能です。インプラント治療を受ける際には、顎の健康との関係も考慮しながら、慎重に治療計画を立てることが重要です。気になることがあれば、遠慮なく歯科医師に相談し、安心して治療を進めていきましょう!
群馬県高崎市のインプラント治療専門
『加藤デンタルオフィス高崎』
群馬県高崎市八島町273 高崎ピュアビル4階
TEL:027-388-0851
*監修者
*経歴
樹徳高等学校卒業。日本歯科大学 新潟歯学部卒業。
医療法人社団 朋優会 ソフィア歯科インプラントセンター 分院長
医療法人MSO かとう歯科 理事長・院長
*所属学会・研究会
・日本顎咬合学会 認定医
・国際口腔インプラント学会(ISOI)ドイツ口腔インプラント学会 認定医
・国際口腔インプラント協会(IDIA)認定医・専門医・指導医
・インディアナ大学医学部解剖学 認定医
・インディアナ大学 インプラント研究員
・日本インプラント学会 会員
・日本歯周病学会 会員
詳しいプロフィールはこちらより